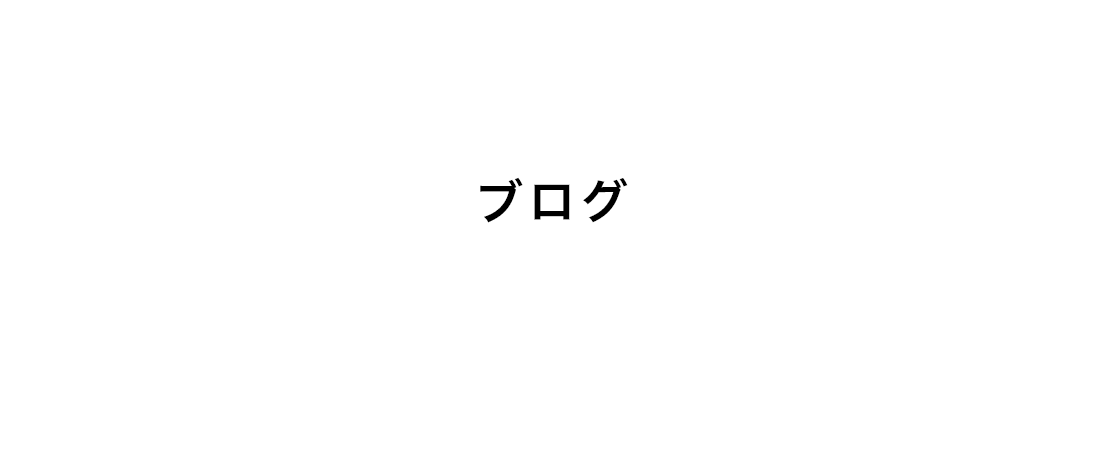皆さんこんにちは! カド建株式会社、更新担当の中西です。
“見えない工程”
なぜクレームは起きるのか?多くは“下地”で決まる
塗装の仕上がりは、塗る技術だけでは決まりません。実は下地処理が 8 割と言われるほど、下地が品質を左右します。ケレン、洗浄、素地調整、補修、シーリング、含水率、錆の状態…。ここが甘いと、どんな高級塗料でも早期劣化につながります。⚠️
現代は顧客の情報量も増え、『高い塗料=長持ち』という誤解が起きやすいです。だからこそ、塗料より先に下地の重要性を説明できるかが信頼になります。️
材料の多様化:選定ミスが増える時代
塗料はシリコン、フッ素、無機、遮熱、低汚染、ラジカル制御など種類が増え、用途も多様です。良いことですが、現場条件(下地、旧塗膜、環境)に合わない選定をすると、密着不良や艶ムラが起きることがあります。
また、メーカーの仕様(希釈率、塗布量、塗り重ね間隔、使用期限)を守る運用が必要です。忙しい現場ほど“感覚”で進めるとブレが出ます。だからチェックリストと標準手順が効きます。✅
天候と乾燥:現代は“極端気象”で難易度が上がる ☀️️
猛暑や高湿度、急な雨、強風…。現代は施工条件が厳しくなっています。乾燥不足は膨れや白化、艶引けにつながり、強風は塗料飛散のリスクを高めます。⚠️
工程を守るには、天候判断の基準を会社として持つことが大切です。『雨が降りそうだから急ぐ』ではなく、『安全と品質のために止める判断』ができる会社が信頼されます。✅
“保証”の課題:期待値調整ができないと揉めやすい
塗装は、素材や環境で劣化速度が変わります。日当たり、海沿い、交通量、雨掛かり、下地状態…。
だから保証の考え方も“条件付き”にならざるを得ません。
揉めるのは、契約前に期待値が揃っていないときです。『保証範囲』『対象外』『点検頻度』『メンテナンス』を事前に説明し、書面化するほどトラブルは減ります。✅
クレームを減らす“見える化”:写真・記録・説明
顧客が安心するのは、工程が見えることです。高圧洗浄、ケレン、下塗り、中塗り、上塗り、膜厚、シーリング。写真で工程を示し、『何をしたか』を短く説明するだけで納得度が上がります。
また、現代は SNS の時代。トラブルが拡散しやすいからこそ、事実を示せる会社が強い。記録は守りであり武器です。️
標準化のコツ:全部やらず“最低限セット”を決める
完璧主義は続きません。まずは最低限セットを固定します。
・図面/仕様確認(塗料・色・艶・範囲)
・下地チェック(劣化・錆・含水)
・工程写真(洗浄→下地→下塗り→上塗り→完了)
・引き渡し説明(注意点・点検)
この 4 点だけでも品質と信頼は大きく変わります。✅
まとめ:品質は『塗る前』で決まる。説明できる現場が勝つ
現代の塗装業は、材料の知識と下地の目、そして説明力が価値になります。見えない工程を見える化し、標準化でブレを減らす。これがクレームを減らし、利益を守る最短ルートです。
次回は、原価上昇・価格競争・受注の取り方など『経営課題』と改善のヒントをまとめます。
追加:下地診断の精度が受注を左右する—“診断力”が価値になる
顧客が塗装会社を選ぶとき、単に価格だけでなく『診断が丁寧か』を見ています。写真を撮って説明する、劣化の種類(チョーキング、クラック、剥離、錆)を分かりやすく伝える。これができる会社ほど信頼されます。
追加:劣化別の基本対応(現場で使える整理)
・チョーキング:旧塗膜が粉化→洗浄+下塗り選定が重要
・ヘアクラック:微細割れ→下地調整+弾性の検討
・構造クラック:動く割れ→補修工法と原因確認が必要
・錆:再発しやすい→ケレン+錆止め+膜厚管理が重要
この整理を持つだけでも、提案がブレにくくなります。✅
追加:膜厚の課題—“塗った感”ではなく“規定量”
膜厚不足は早期劣化の大きな原因です。忙しいと『薄く伸ばしてしまう』ことがありますが、規定量を守るほど結果的に手直しが減ります。塗布量を現場で共有し、ローラーやスプレーの設定を固定化するのがコツです。
追加:色・艶のトラブル—事前の合意が 9 割
色はモニターや紙見本で印象が変わります。現場で揉めないためには、
・試し塗り(可能なら)
・艶の指定(艶あり/3 分/艶消し)
・光の当たり方で見え方が変わる説明
を事前に行うのが重要です。✨
追加:工程管理の“段階ゲート”
・下地完了ゲート:補修と清掃、含水、錆の状態
・下塗りゲート:塗布量、乾燥、密着
・上塗りゲート:仕上がり、ムラ、清掃
止める場所を決めると、後工程のトラブルが減ります。✅
追加:提出物の負担を下げる“テンプレ固定”
写真の命名(現場名_日付_工程番号)とフォルダ構成(見積/施工/完了/保証)を固定すれば、誰でも手伝えます。職長の負担が減り、現場が回ります。✨
追加:下地の“含水”と“汚れ”が密着を壊す
外壁や木部、モルタルは含水が高いと密着不良の原因になります。洗浄後は十分乾燥させ、必要なら含水計で確認する。乾燥を待つのは遠回りに見えて、手直しを減らす最短ルートです。✅
追加:旧塗膜との相性—“上に塗る”ほど難しい
旧塗膜が何か分からないと、相性でトラブルが起きます。可能なら過去の仕様を確認し、密着テスト、下塗り選定でリスクを減らす。ここを丁寧にすると、保証トラブルも減ります。
追加:顧客の安心を増やす“説明の順番”️
①現状(写真)→②原因→③対策→④工程→⑤費用→⑥注意点
順番が整うほど、納得度が上がり、値引き交渉が減ります。✨
追加:写真提出の最小テンプレ(これだけで十分)
・洗浄前後
・下地補修
・下塗り
・上塗り
・完了全景
この 5 点を固定化すると、説明が早くなり、社内の共有もラクになります。✅
追加:施工条件の“見落とし”チェック(現場前に確認)✅
・日陰か日向か(乾燥速度が変わる)☀️
・風が強いか(飛散リスク)️
・湿度が高いか(白化・乾燥不良)
・近隣距離が近いか(養生強化)
・車両動線と駐車が確保できるか
・電源・水の使用可否
このチェックを見積段階で行うほど、現場は安定します。
追加:鉄部・木部での注意点(簡単まとめ)
【鉄部】錆の除去と錆止め、膜厚の確保が最重要。錆が残るほど再発が早い。
【木部】含水と割れ、塗料の浸透性がポイント。乾燥を待てる工程設計が重要。
追加:完了検査の“見るポイント”
・ムラ、塗り残し、タレ、ピンホール
・養生剥がし跡、飛散、汚れ
・シーリングの仕上がり
・清掃(周辺含む)
検査の視点を共有すると、品質が安定します。✅✨
追加:見積前の“簡易診断チェックシート”例
【外壁】チョーキング/クラック/シーリング劣化/汚れ
【屋根】色あせ/苔/錆/板金浮き
【付帯】雨樋/破風/鉄部錆
【環境】日当たり/風/海沿い/交通量
【近隣】距離/駐車/洗濯物/作業時間
このシートを使うと診断が抜けにくくなり、説明もしやすくなります。✅
追加:顧客に渡す“メンテナンスの一言”例 ️
『強風後は落枝や飛散物がないか見てください』
『雨だれ汚れは早めに拭くと定着しにくいです』
『コーキングの割れを見つけたら早めに相談ください』
短い一言が、次の信頼につながります。✨
――――――――――――――――――――
この記事が、塗装業に携わる皆さまの『安全・品質・利益・働き方』を同時に高めるヒントになれば幸いです。�
お問い合わせはこちら↓
カド建株式会社