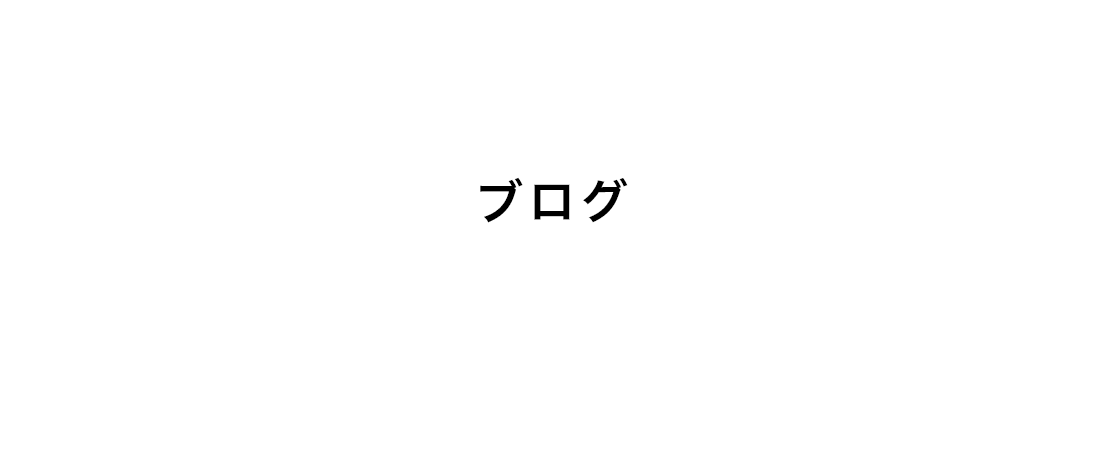皆さんこんにちは!
カド建株式会社、更新担当の中西です。
さて今回は
~色彩ガイドライン~
ということで、
今回は、塗装業において重要な役割を果たす「色彩ガイドライン」について深く掘り下げてご紹介します。
建物の外壁や屋根に使われる色は、その建物だけの問題ではありません。町の景観、文化、そして暮らす人々の感覚にまで影響を与えるものなのです。
そうした公共性と調和性を重視するために、多くの自治体や地域団体では「色彩ガイドライン」が設けられています。これは、美しいまち並みを守り、持続可能な景観をつくるためのルールと知恵なのです。
色彩ガイドラインとは?
色彩ガイドラインとは、建物の外装(外壁・屋根など)に使用する色やデザインに関して、地域ごとの景観調和や美観保護を目的として定められた指針・基準です。
制定主体:
法的拘束力がある「条例」に基づくものもあれば、推奨ベースの「指針」「設計ガイドライン」形式のものもあります。
ガイドラインが重視される背景
なぜ色にルールが必要なのか?
-
景観の統一性を保つ
-
歴史的・文化的景観の保全
-
観光資源や不動産価値の保護
ガイドラインで定められる内容の一例
| 項目 |
内容 |
| 色相 |
周囲と調和する自然色(ベージュ、ブラウン、グレーなど)推奨 |
| 彩度 |
派手な原色・高彩度色は禁止または制限 |
| 明度 |
白すぎる・黒すぎる色は避けるよう指導される場合あり |
| 光沢 |
ツヤありは禁止、マット仕上げを推奨 |
| 屋根材・外壁材の素材感 |
地元の伝統素材(瓦、漆喰、木材風)との調和重視 |
| 看板・装飾 |
店舗などでは外装にあわせた控えめな配色が求められる |
実例:地域ごとのガイドライン
-
京都市:「屋根は伝統色に限る」「外壁は落ち着いた中間色で」
-
鎌倉市:神社仏閣周辺での色調・明度制限あり
-
金沢市:「ひがし茶屋街」などの歴史的景観保全区域では色彩審査が必要
-
東京・武蔵野市:再開発地区での景観計画協議が義務化
地域の“らしさ”を大切にするため、自由な色選びではなく、文化的対話が求められます。
塗装業者としての対応と責任
施工前に確認すべきこと:
-
その地域に色彩ガイドラインがあるか
-
申請・届出が必要か(景観条例に基づく協議)
-
既存の建物とのバランスを考慮しているか
-
施主にガイドラインの存在を説明しているか
塗装業者は、ただ“色を塗る”のではなく、**地域と調和した「街の設計者の一部」**としての意識が求められます。
ガイドラインと住民・施主のすれ違い
よくあるギャップ:
このような場面では、事前にガイドラインを説明し、納得の上で色選びをサポートすることが大切です。
今後の課題と展望
ガイドラインの標準化とわかりやすさ
デザインと景観の共存
おわりに──「塗ること」は、街と文化をつなぐこと
色彩ガイドラインは、「美観の押し付け」ではありません。それは、地域の記憶と未来を守るための“色の言葉”です。
あなたが選ぶ色が、
その街の空気や景観を、10年後も支えているかもしれない。
塗装業におけるカラー選定は、技術とセンス、そして地域との調和が試される仕事です。美しく、そして意味のある一色を、プロとしてご提案していきましょう。
お問い合わせはこちら↓
カド建株式会社